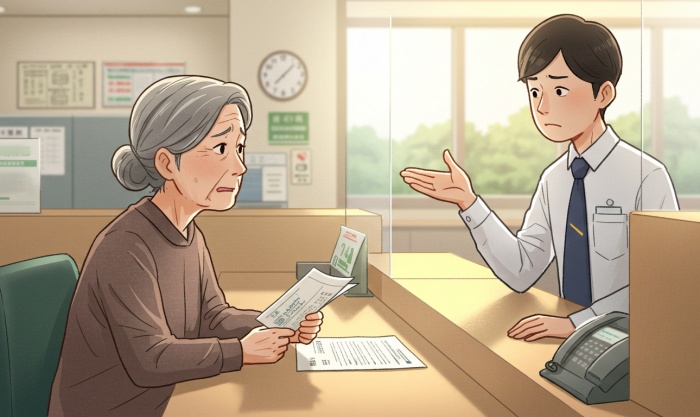「ちょっとそこまで」と出かけたまま、家に帰ってこない…
そんな状況が突然訪れたら、と考えるだけでゾッとしますね?
ただ、認知症の家族が行方不明になるケースというのは決して珍しくありません。
警察庁の統計によると、認知症やその疑いがあり、家族などが警察に捜索願を出した行方不明者は、毎年18,000人以上というデータがあります。
この記事では、実際の事例や、行方不明が発覚した際に警察へスムーズに伝えるべき情報など、調べた情報をもとにまとめました。
いざというときに冷静に対応できるよう、ぜひ参考にしてください。
認知症による行方不明の実態
認知症の人が行方不明になる原因とは?
認知症の人が行方不明になる背景には、もちろん記憶障害や判断力の低下が深く関係しています。
自宅や普段の生活圏であっても、自分がどこにいるのかわからなくなり、その場から離れようとして迷子になってしまうケースが多いです。
特に以下のような状況では、行方不明になるリスクが高まります。
- 住んでいた家に帰ろうとする(記憶の混乱により、現在の住所が分からなくなる)
- トイレを探して外に出る(室内で迷い、外へ出てしまう)
- 「仕事に行かないと」と思い込む(過去の習慣が突然よみがえり、外出する)
- ストレスや不安を感じて徘徊する(認知症の進行による精神的不安定が影響)
また、夕方から夜間にかけて症状が悪化しやすい「夕暮れ症候群」と呼ばれる現象もあり、暗くなると落ち着かずに外へ出てしまうこともあります。
これらの原因を頭に入れておくだけでも、適切な対策をとるための1つのきっかけになるかもしれません。

行方不明になったときの統計データと発見率
認知症による行方不明は年々増加しており、警察庁のデータによると、2023年には1万9000人以上の行方不明届を出されていることが報告されています。
この数は年々増加傾向にあり、高齢化が進む日本では今後さらに増える可能性が高いです。
行方不明になった人の発見率は高いものの、発見までの時間が長引くケースでは事故や体調悪化のリスクが高まるので、早急な対応が求められます。
【発見までの時間と生存率の関係】
- 6時間以内の発見⇒生存率ほぼ100%
- 24時間以上発見されなかった場合⇒事故や体調悪化のリスク増加
とくに、冬場と夏場は気温の影響で体力が奪われやすく、危険度が高まるため、発見までのスピードが重要です。
実際に起きた認知症徘徊の事例
ここでは、実際にあった認知症徘徊の事例を紹介します。どのような行動パターンがあるのかを理解し、早期発見のための参考にしましょう。
事例1:夜間に家を出てしまい数十キロ先で発見
ある夜、高齢の男性が寝ている間に家を抜け出し、家族が気づいたときにはすでに姿がありませんでした。 捜索が開始されたのは翌朝。近所を探しても見つからず、警察に届け出をしたものの、最終的に発見されたのは約30km離れた隣の県の公園でした。
【対策のポイント】
- 夜間に出入りできない対策をする(鍵の二重ロック、センサー設置)
- 近隣住民に徘徊の可能性を伝えておく
事例2:電車で遠くまで移動し、身元不明で保護
認知症の女性が、普段利用していた電車に乗り込み、そのまま長距離移動。駅のホームで保護されたときには、自分の名前や住所が言えず、警察でもすぐに身元が特定できませんでした。家族が行方不明届を出してから約12時間後、ようやく発見されました。
【対策のポイント】
- 身元を特定しやすいように「連絡先を書いたタグ」や「GPSを持たせる」
- 公共交通機関を利用する可能性がある場合は駅員に相談しておく
事例3:短時間の外出がそのまま行方不明に
家族が少し目を離したすきに、高齢の男性が「散歩に行く」と言い残して外出。そのまま行方不明となり、発見までに約36時間かかりました。途中で道に迷い、さらにパニックになり、どこに向かえばいいのか分からなくなってしまったといいます。
【対策のポイント】
- 普段から外出時には見守り用のGPSを持たせる
- 散歩ルートを把握し、行きそうな場所をリストアップしておく
共通するポイントと対策の重要性
上記の事例に共通しているのは、「外に出る際のルールがない」「すぐに発見できる仕組みがない」という点です。
認知症の行方不明を防ぐためには、事前の対策と発見までのスピードが重要です。
- ドアの施錠を工夫し、簡単に外へ出られないようにする
- GPS端末を持たせ、すぐに居場所を特定できるようにする
- 万が一の際に備え、警察や地域住民との連携を強化する
次に、行方不明が発覚した際に、警察へどのように連絡し、何を伝えるべきかを解説していきます。
認知症の家族が行方不明になったらまずやるべきこと
迷ったらすぐに警察へ連絡すべき理由
認知症の家族が行方不明になったとき、「もう少し探してから警察に連絡しよう」と考える方も多いかもしれません。
しかし、認知症による行方不明は時間が経つほど発見が難しくなり、命に関わるリスクが高まるため、できるだけ早く警察へ連絡することが重要です。
実際に、警察庁のデータでは6時間以内に発見された場合の生存率はほぼ100%ですが、24時間以上経過すると死亡リスクが大幅に上昇することがわかっています。
とくに、気温が低い冬場や、熱中症の危険がある夏場は早急な捜索が必要です。

我が家でも、昼間に出て行くことが多いので、夏場の熱中症は心配です
また、警察に届け出ることで、『行方不明者届』が受理され、地域の警察や関係機関が協力して捜索を行うことになります。
当然多くの目が捜索に加わることになるので、発見の可能性が高まります。
「もしかしたらすぐ戻ってくるかも」「迷惑をかけたくない」と躊躇せず、「いつもよりも長いな…」と感じたらなるべく早めに警察に相談することをおすすめします。
警察に伝えるべき重要な情報
警察に行方不明の届け出をする際には、以下の情報をできるだけ正確に伝えることが大切です。あらかじめメモを用意しておくと、スムーズに対応できます。
- 行方不明者の基本情報を伝えます。身元特定のため、できるだけ正確に伝えましょう。
- 外出時に着ていた服の色や特徴を詳しく伝えます。特に目立つ柄や小物(帽子、バッグ、靴の種類など)があれば、発見の手がかりになります。
- 例:「青いチェックのシャツに黒のズボン。白いスニーカーを履いています。」
- 最後に目撃した時間や場所を警察に伝えます。たとえば、「午後2時に自宅を出た」や「駅の改札を通ったのを最後に見ていない」といった情報が役立ちます。
- 「いつも行く場所」や「よく歩くルート」がわかると、警察も捜索しやすくなります。たとえば、近くの公園や昔住んでいた場所、馴染みのスーパーなどを伝えましょう。
- 高血圧や糖尿病などの持病、転びやすいなどの身体的特徴がある場合は、必ず伝えます。寒暖差に弱い、長時間の歩行が困難、夜間視力が低下するなどの特記事項は重要です。
- GPS端末やスマホを持っている場合は、位置情報の確認方法を伝えましょう。例えば、「あんしんウォッチャーを持っており、最後のGPS記録は○○公園の近く」といった情報が捜索の手がかりになります。
【氏名・年齢・性別】
【服装や持ち物】
【行方不明になった時間と場所】
【普段の行動パターン】
【持病や体調などの注意点 】
【GPSや見守りツールの有無】
警察に伝えるときのポイント
警察に行方不明の届け出をする際は、ただ「家族がいなくなりました」と伝えるだけではなく、いつもよりも長く行方が分からなくなっている場合は早期に捜索を開始してもらうための工夫が必要です。
この辺りの判断は難しいと思いますが、本当に切羽詰まっている場合は、「認知症の影響で迷子になっている可能性があり、命に関わる状況です」と明確に伝えることで、警察も迅速に動いてくれるはず。
とくに冬場や夏場、夜間であれば「気温や健康状態の影響で危険な状態」と強調すると効果的だと思います。

過去の徘徊履歴があれば共有
以前にも徘徊したことがある場合は、発見された場所やそのときの状況を伝えましょう。
警察にも記録が残っているはずですが、「以前は○○公園で発見された」や「昔住んでいた△△町の方へ向かったことがある」といった情報があれば、警察の捜索範囲を絞り込む手がかりになります。
最低限のマナーは守る
行方不明になる度に警察に捜索をお願いするのは、迷惑を掛けるだけでなく、日頃の対策不足と言わざるを得ません。
なので、最低限のマナーとして、GPS端末の活用や衣服への名前の記載など、日々の予防と対策を怠らないようにしましょう。
110番通報ではなく、最寄りの交番に行くというのもマナーの1つと言えるかもしれません。
ただ、たしかに警察の方にあまり迷惑を掛けたくないという気持ちもありますが、もしものことがあったときに後悔しない行動は取っておくべきだと思います。
【あわせて読みたい】
認知症の行方不明を防ぐための対策
認知症による行方不明は、事前の対策をしっかり行うことで予防できるケースが多くあります。ここでは、家族ができる日常的な対策と、便利なグッズについて紹介します。

家族ができる日常の予防策
行方不明を防ぐためには、まず日常生活の中でできる工夫が大切です。認知症の人が家を出るのを防ぐ対策や、万が一外出してしまったときに早く発見できる工夫を取り入れましょう。
ドアに対策をする(鍵の工夫、チャイム設置)
認知症の人が気づかないうちに外出してしまうのを防ぐには、玄関や勝手口に工夫をすることが重要です。
- ドアの鍵を普段とは違う場所につける(高い位置や隠し扉)
- センサー付きチャイムを設置し、ドアが開くと家族に通知が来る
- 夜間の外出を防ぐために、ドアの前に障害物を置く
とくに「鍵をかけるだけでは防ぎきれない」と感じている方は、自動施錠機能がついたスマートロックや、ドアの開閉を通知するセンサーを活用するとより効果的です。
衣服や靴に名前や連絡先を記入
万が一外出してしまったときに、早く身元を特定できるようにする工夫も必要です。
- 上着の裏側に名前や連絡先を書いた布を縫い付ける
- 靴の内側にラベルを貼る(靴を履いていれば連絡先がわかる)
- 帽子やカバンにも名前を記入
最近では、QRコードシールを衣類に貼ることで、スマホで読み取ると家族に連絡がいく仕組みのものもあります。
警察や保護施設で身元不明の高齢者が見つかった際、連絡先がわからずに保護されるケースが多くあります。
QRコードシールを活用すれば、第三者が発見したときにすぐに家族と連絡が取れるため、発見後の対応がスムーズになります。
近隣住民と情報共有しておく
認知症の方がいることを近所の方に伝えておくと、行方不明時に早期発見につながることがあります。
- 普段の行動範囲を知ってもらう
- 「もし見かけたらすぐ連絡をください」とお願いする
- 町内会や自治体の見守り制度を活用する
最近では、地域ぐるみで高齢者を見守るネットワークがある自治体も増えてきています。近所に頼れる人がいると、行方不明時の捜索範囲も広がるため、早めに相談しておきましょう。
GPS端末や見守りサービスの活用
認知症の行方不明を防ぐには、GPS端末を持たせて居場所をリアルタイムで把握することができます。
【GPSの種類と選びときのポイント】
- リアルタイムで位置が分かるタイプ(スマホアプリで居場所を確認可能)
- 一定間隔で位置情報を記録するタイプ(移動履歴を確認できる)
- 家を出たら通知が来るタイプ(ジオフェンス機能付き)
選ぶ際は、バッテリーの持ちや、防水性能、使いやすさを考慮するとよいでしょう。
管理人も実際に使っている「あんしんウォッチャー」は、位置情報をリアルタイムで確認できるGPS端末です。
- スマホアプリからいつでも居場所を確認できる
- 移動履歴を記録し、どこを歩いたか把握できる
- 家を出たときに通知が来る機能がある
【あわせて読みたい】
「行方不明になってから探す」ではなく「リアルタイムで動きを把握できる」、もしくは「外出した瞬間に気づく」ことができるのが強みです。
徘徊が始まる前に対策を打つことができるため、家族の負担が大幅に軽減されますよ。
【まとめ】できるだけの対策をしてストレス軽減へ
認知症の症状がある家族にとって「行方不明」は、いつでも誰にでも起こり得る身近な問題です。

日々の生活にストレスを感じて、辛い日々がいつまで続くのか途方に暮れますよね。
しかし、その対策をしておくだけで、早期発見や未然防止が可能になってストレスはかなり減ります。
今回の記事ではこのようなことを解説してきました。
- 行方不明になったと気づいたら、**迷わずすぐに警察へ連絡**することが最優先です。とくに、気温の変化が激しい季節や、交通量の多いエリアでは危険度が高まるため、発覚から30分以内には警察へ届け出ることを推奨します。
- 行方不明の届け出をスムーズに進めるには、服装・持ち物・行動パターン・持病などの情報を整理し、警察に正確に伝えることが大切です。「単なる徘徊」ではなく「命に関わる緊急事態」であることを強調すると、より早く動いてもらいやすくなります。
- 日頃から、玄関の施錠強化やセンサーの設置、近隣住民との情報共有、衣服への連絡先記入といった対策を行うことで、行方不明のリスクを大幅に減らせます。
- 徘徊対策として、GPS端末やQRコードシール、音声通話機能付き見守りデバイスを導入するのも効果的です。管理人も活用している「あんしんウォッチャー」は、外出時の位置情報をリアルタイムで確認でき、家族の負担を大きく軽減してくれます。
【行方不明が発覚したら即対応が重要】
【警察へ迅速に正確な情報を伝えることが鍵】
【事前の対策で徘徊を防ぐことも可能】
【GPSや見守りグッズを活用し、家族の負担を減らす】
本当に、もしものことがあったときに後悔はしないためにも、「行方不明になってから探す」ではなく「そもそも行方不明にならないようにする」という視点で、事前にできる対策をしっかりと行い、大切な家族を守っていきましょう。
関連記事:認知症対策GPSに【あんしんウォッチャー】毎日使ってます!体験談まとめ